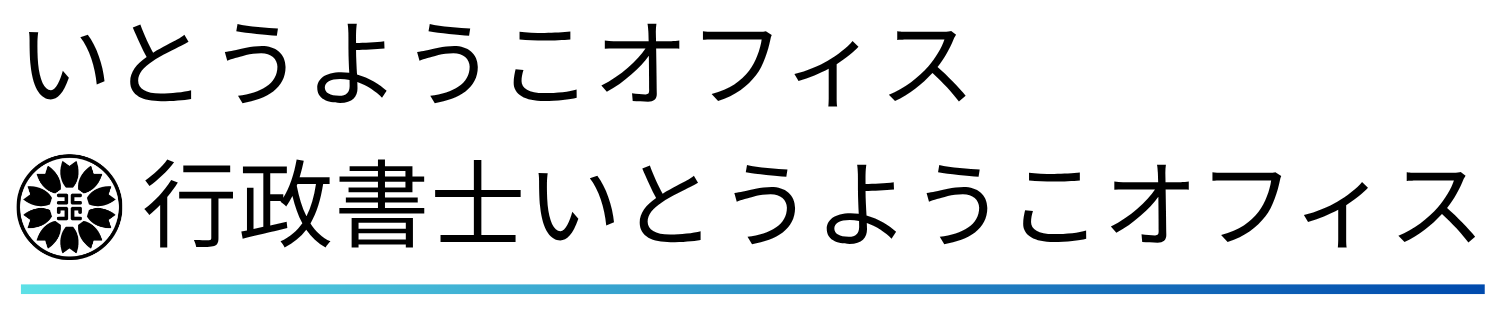「身分証明書」とは何か?
「身分証明書」といえば、本人確認をするために提示するもので、個人番号カード(マイナンバーカード)や運転免許証、パスポート、健康保険証など、公的機関が発行した証明書を指すと一般的には考えられています。
しかしながら、本籍地の市町村が発行する「身分証明書」というものが存在します。
おそらくそれを必要とした者以外は、目にすることがないものでしょう。
国家公務員就職時に求められる「身分証明書」
公務員として就職する際に、本籍地の市町村が発行する「身分証明書」の提示が求められました。私はその際、初めて目にすることとなりました。
旧民法で定められていた意思能力や行為能力の欠缺がないか、破産者でないかが記載されており、大学の民法総則の授業で習った無能力者の意味を改めて意識した瞬間でした。
現在の「身分証明書」に記載される3つの項目
今回、たまたま改めて「身分証明書」を取り寄せたところ、記載されていたのは以下の3点でした。
① 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
② 後見の登記の通知を受けていない
③ 破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない
① の記載については、禁治産者と準禁治産者が、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149 号)が成立したことで、廃止となりました。つまり、現在の身分証明書に記載されている内容は、平成12年3月31日時点での事実を記載しているにとどまっています。
現状はどうなっているか
では、その後の状況はどのようになっているのでしょうか。
新たな民法では、制限行為能力者として、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が定められました。そして、新たに任意後見契約に関する法律(平成11 年法律第150 号)も定められ、平成12年4月1日から成年後見制度がスタートしました。
それに伴い、後見登記等に関する法律(平成11 年法律第152 号)が制定されたことで、①に該当する内容は、平成12年4月1日法務局が登記することになりました。
現在、成年後見(法定後見及び任意後見)を受けていないことは、法務局の戸籍課で発行する「登記されていないことの証明書」をもってなされることになっています。平成12年3月31日以前に生まれた人が、これまでに民法上の無能力者・制限行為能力者となっているかどうかを証明するには、市町村の発行する「身分証明書」及び法務局が発行する「登記されていないことの証明書」の両方が必要ということになります。