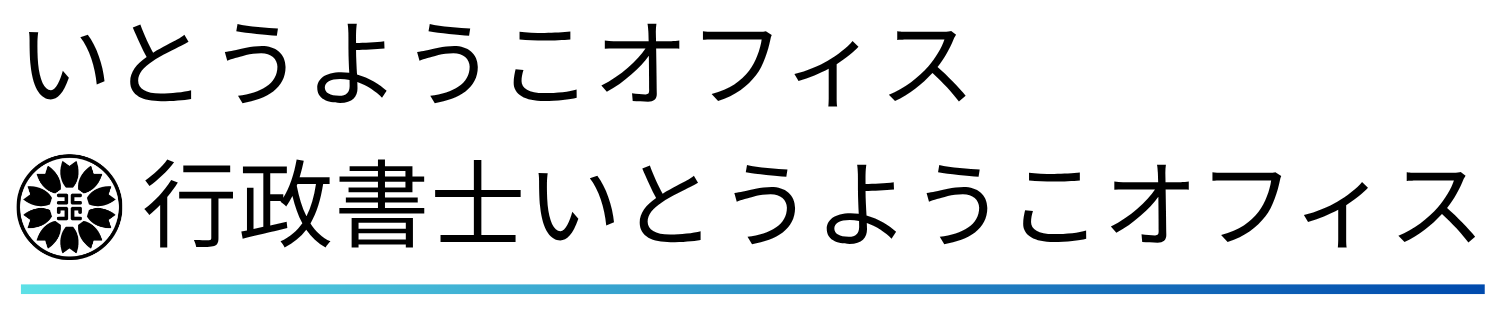最近の議論:文科省での取り組み
最近の科学技術コミュニケーションについて取り上げます。
2025年5月19日に開催された文部科学省の科学技術・学術審議会人材委員会では「今後の科学技術・人材政策の基本的方向性について」が議題とされていました。資料1-2⑤の「科学技術コミュニケーションに関する現状・課題・今後の方向性(案)」という資料が気になりました。
https://www.mext.go.jp/content/20250516-mxt_kiban03-000042600_6.pdf
これまでこのような資料は気にも留めなかったのですが、非常に興味深かったので、後ほど議事録でその議論の内容を確認したと思います。
北海道大学の科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)が科学技術コミュニケーターを養成する講座を提供していると記載があり、昨年1年間、私自身こちらでサイエンスライティングを学び、科学技術コミュニケーターの一人として歩み始めたところです。
資料の冒頭には、基本的な考え方として「科学技術がもたらす倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)なども含めた、時代に即した科学技術コミュニケーションを推進し、科学技術と社会の関係を深化させていくことが必要」と述べられています。自分自身も「知的財産や経済安全保障の分野で研究者等が安心して研究開発、技術開発、社会実装を進められるよう、研究者等のリテラシー向上に向けて大事なこと、気を付けるべきこと、危険なこと等について、ブログや業界紙の記事の執筆等を通じた発信をしていきたい」と修了に当たってのレポートで記載したところであり、まさに求められていたことを学んでいたのかもしれないと考えています。
人材育成の課題として、「理工系の人材だけでなく、人文系人材が科学技術コミュニケーションにさらに関わることが必要」と指摘もある。まさに私自身が人文系の人間であり、1年間の学びを通じて吸収できることは非常に多かったし、対話を通じて得られる気づきも多く得られ、これから私にできることもあるのではないかと考えています。
個人としての関心と実践
文系なのになぜ科学技術コミュニケーションなんて学ぶのか?という質問には、世の中数多いる者すべてが研究者・専門家ではないので、わかりやすく嚙み砕いた説明が必要な場面があることや研究者が知っておいたほうがよい知識が備わっていない場合もあり、研究者に対する理解増進活動もあって良いのではないかと答えてきており、私自身そのように感じています。